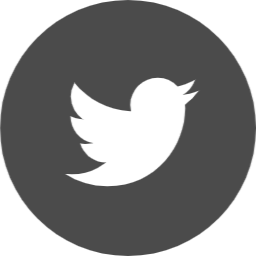片頭痛患者さんが我慢せずに医師に相談、適した薬剤を選択できるようになるには‐【自主調査第1回:片頭痛患者さんの実態について】
2025/07/05 メディリード / マーケティング&コミュニケーション部
メディリード / マーケティング&コミュニケーション部
日常生活に支障をきたす片頭痛。多くの人が「我慢」で乗り切っている現状に対し、メディリードでは約6,700人を対象に実態調査を行いました。
先日公開した記事「【片頭痛患者さん調査】医療機関受診、薬剤選択、服用を進めるために必要なこととは」では、調査の全体像をお伝えしました。本記事では、シリーズの第1回として、片頭痛患者さんの属性や症状、受診・服薬について詳しく見ていきます。
目次
背景
日本では、片頭痛の年間有病率は8.4%と報告されており1)、社会的、経済的にも大きな影響を及ぼす疾患と言えます。一方で、片頭痛症状があるにもかかわらず、一度も医療機関を受診していない人が多く存在します。その理由として、「受診するほどではない」と考え、市販薬で対処できると判断していたり、痛みを我慢したりするなど、「片頭痛のスティグマ(偏見)」の存在が指摘され、近年注目を集めています。
片頭痛は、医療機関を受診し薬物治療を受けることで症状の軽減が期待できるほか、起こる回数や頻度を減らす、症状を軽くするといった予防治療も可能です。しかし、実際には予防薬を使用している人も少ないのが現状です。そこで私たちは、片頭痛患者さんにおける受診状況や薬物治療の実態、さらには患者さん自身が片頭痛に対して抱く意識や行動に注目し、その背景を明らかにするための調査を実施いたしました。
本記事では、その中でも特に注目すべき結果を抜粋してご紹介していきます。
調査概要
| 調査手法: | インターネット調査 |
| 調査地域: | 全国 |
| 調査対象: |
片頭痛と診断されている、もしくは片頭痛の症状を持っている人、かつ下記の条件を満たしている人
|
| 調査期間: | 2024年10月22日(火)~2024年10月30日(水) |
| 有効回答数: | 6,753 |
※調査結果は、端数処理のため構成比が100%にならない場合があります
調査課題
私たちは、今回の調査で以下の点を明らかにすることを試みました<図1>。
<図1>
- どうしたら未受診患者さんが市販薬で我慢せず、受診して治療開始したいと思うか
- どうしたら患者さんが片頭痛治療薬を選択し、医師に相談したいと思うか
- どうしたら患者さんが予防治療薬を選択し、医師に相談したいと思うか
これらの課題は、調査課題としては次のように置き換えることができます。
- 片頭痛症状における医療機関受診、薬剤の選択、服用においての障壁、もしくはドライバーは何か?
本レポートのテーマ
本レポートでは、先に挙げた調査課題を明らかにするため、5つのテーマを設定し、各回に分けてトピックを取り上げていきます。
具体的なテーマは以下の通りです<図2>。
<図2>
第1回:片頭痛患者さんはどのような人たちか?
第2回:受診する/しないのはなぜか?
第3回:患者さんが片頭痛に関する情報を知ることで、相談意向は変化するか?
第4回:薬剤選択において、患者さんの意向はどのくらい反映されているか?
第5回:患者さんは処方薬にどれくらい満足しているか?希望する薬があれば相談するのか?
第1回の今回は、「片頭痛患者さんはどのような人たちか?」について取り上げ、主に属性や患者さんの症状、受診の状況などについて見ていきます。
回答者属性
本調査回答者の属性は以下の通りです。
<図3>
第1回レポートサマリー
<図4>
調査結果詳細
片頭痛患者さんはどのような人たちか?
片頭痛患者さんの実際の受診状況や服薬状況はどうなっているのでしょうか。
また、患者さんの症状や生活への支障はどの程度なのでしょうか。
前述した通り、症状があっても我慢している「片頭痛のスティグマ」を抱える患者さんの存在が知られていますが、今回の調査結果と照らし合わせ、より具体的に状況を見ていきたいと思います。
受診状況、服薬状況
まずは片頭痛患者さんの受診状況、服薬状況を概観してみます<図5>。
<図5>
本調査の対象者は、診断の有無は問わず片頭痛症状のある患者さんです。そのうち、受診経験のある人(受診経験あり者)は62.7%、ない人(受診経験なし者)が37.3%でした。
また、受診経験あり者のうち、1年内に受診したことがある人(1年内受診あり者)は27.0%で、3割に満たない状況でした。受診をしても約7割は通院をやめてしまったことになります。
薬の服用状況を見てみますと、片頭痛薬使用者は15.7%、予防薬使用者はその半分の7.6%でした。片頭痛薬で治療している人はわずかで、その中でも予防薬を使用している人はかなり限られていることがわかります。
受診状況、服薬状況を切り口に患者さんを7つのセグメントに分けました(<図5>で番号記載をしている群がそれに該当します)。
①受診経験なし者
②1年内未受診者
③1年内受診あり者
④片頭痛薬使用者
⑤予防薬使用者
⑥予防薬非使用者
⑦解熱鎮痛剤使用者
レポート内で言及していないセグメントもありますが、図表にはすべて掲載していますので、参考情報としてご覧ください。
属性特徴
セグメントのプロフィールを性別、年代別に見ると<図6>のようになりました。
<図6>
全体での男女比はおよそ4:6でした。
セグメントごとに男女比を見てみると、①の受診経験なし者は女性の割合が多い(全体の62.1%に対し67.5%)ことがわかります。さらに受診経験なし者の性年代構成をみると、特に女性30~40代の割合が高いことがわかります。
対して片頭痛薬使用者(セグメント④)、うち予防薬使用者(セグメント⑤)は男性の割合が高めです。全体の37.4%に対し、片頭痛薬使用者は44.7%、予防薬使用者では49.0%となっています。
片頭痛患者さんの中でも特に40代女性は受診に至りにくく、また、片頭痛薬は服用していても予防薬の使用には至っていない人が多いことがうかがえます。
受診先の特徴
続いて、患者さんたちはどのような医療機関や診療科を受診しているのかについて見ていきます。
受診経験のある医療機関を複数回答形式で選んでもらった結果が<図7>です。
<図7>
予防薬使用者は大学病院や国公立病院の割合が高いことがわかります。
対して予防薬非使用者は診療所/クリニックの利用者が多くなっています。
予防薬は大学病院や国公立病院のような、比較的大規模な医療機関で処方される傾向があります。患者さん側にとっても「気軽に受け取れる薬」ではなく、ハードルの高い治療と認識されている可能性があります。
<図8>は、頭痛で受診経験のある診療科を複数回答形式で選んでもらった結果です。
<図8>
予防薬使用者は受診経験のある診療科の数が平均1.81と、全体の1.37と比較して多めです。また、予防薬使用者の頭痛外来の利用率は27.2%と、全体の16.6%と比較して高めですが、精神科・心療内科や神経内科、ペインクリニックなどの利用率も高めです。頭痛外来に加えてこれらの診療科でも予防薬が処方されることが比較的多いことがわかります。
一方で、解熱鎮痛剤使用者は一般内科の受診経験率が51.4%と、全体の46.1%と比較して高めでした。一般内科では頭痛に対して片頭痛薬よりも解熱鎮痛剤が処方される傾向があることがうかがえます。
症状的特徴
片頭痛患者さんはどのくらいの期間、頭痛に悩まされているのでしょうか。セグメント別に見たものが<図9>です。
<図9>
症状に悩んでいる期間の平均は、全体で14年程度でした。受診経験なし者も「20年以上」が4割にのぼっており、長期間頭痛に悩んでいる人でも受診に至っていないことがわかります。片頭痛のある状態が常態化してしまい、我慢するのが当たり前になっている状況が推測されます。
次に、頭痛により支障のある日数(ひと月当たり)を見てみます。「日常生活に支障を与える頭痛や、痛み止めのお薬を服用する必要がある頭痛は、ひと月当たりに何日ありますか?」と尋ねた結果が<図10>です。
<図10>
ひと月あたりの支障日数は、受診経験なし者、1年内未受診者では「5日以内」が7割程度にのぼりました(全体では62.3%)。
一方で1年内受診あり者は平均の支障日数が7日程度と、1年内受診なし者および受診経験なし者の5日程度に比べて多くなっています。この結果から、頭痛により支障のある日数が少い場合、受診に至らなかったり、受診を中断したりする傾向があることがうかがえます。
頭痛時にどのような支障があるのかについて尋ねた結果が<図11>です。
セグメント間の差は小さく、受診や薬の使用のの有無にかかわらず、様々な支障を感じている人が多いことがわかります。
特に、1年内に受診していない人であっても、症状が軽減したわけではなく、支障があるにもかかわらず受診をしていない実態が明らかになりました。
<図11>
予防治療推奨者の割合
頭痛による日常生活への支障度と、ひと月当たりに頭痛が起こる日数から「予防治療が勧められる人」を算出した結果が<図12>です。
<図12>
片頭痛症状のある人全体で9割近くが「予防治療が勧められる人」に該当し、そのうち半数以上は、「予防治療がとても強く勧められる人」でした。
一方で、受診経験のない患者さんが全体のおよそ4割を占めており、症状と推奨される治療との間に大きなギャップがあることが明らかになりました。
頭痛の症状がない時の支障/行動への影響
頭痛の症状がない時に、片頭痛患者さんはどのような支障や影響を感じているのでしょうか。「頭痛の症状がないときのあなたのお気持ちや行動(行動面に起きる支障)について、あてはまるものをお選びください。」と尋ね、複数回答形式で選んでもらいました<図13>。
<図13>
片頭痛薬は使用しているものの予防薬を使っていない人では、「頭痛が起こりそうだと感じたら、すぐに薬や休養などで対策をとる」と回答した割合が53.5%と、全体の43.5%と比較して特に高くなっています。
まとめ
今回は「片頭痛患者さんはどんな人たちか?」について、患者さんの属性や受診状況、服薬状況などを概観しました。
その結果、改めて「片頭痛のスティグマ」の存在が浮き彫りになりました。
受診に至っていない人では特に30代~40代の女性が比較的多い傾向にありました。この年代は、子育てや仕事と家庭の両立など多忙なライフステージにあることが多く、症状を軽視したり、自分の健康を後回しにしたりしている可能性が考えられます。
また、未受診者は支障のある日数が少ない傾向があることから、支障はあったとしても市販の頭痛薬使用により「その場をやり過ごす」ことが常態化しているか、もしくは症状の過小評価につながっていることが考えられます。
患者さん自身が「自分の片頭痛症状は決して軽症ではなく、日常生活にも支障がある状態である」ことを認識し、「自分は適切な治療を受けることでもっと生活の質を上げられる」と思い描けるようになることが、患者さんの日常生活の質を向上するためにまずは重要と思われます。
次回以降は、患者さんが薬物治療にあたりどのような不安を抱えているのか、その不安はどう解決されているのかについてみていきたいと思います。
1) Sakai F, Igarashi H. Prevalence of migraine in Japan : a nationwide survey.
Cephalalgia 1997; 17(1):15-22.
メディリードのヘルスケアデータベースは、国内最大規模の疾患に関するアンケートデータであり、(1)一般生活者の疾患情報に関する大規模調査、(2)何らかの症状・疾患で入通院中の方の主疾患に関する深掘り調査(追跡調査)から構成されています。回答者への追跡調査は、より深いインサイトの獲得を可能にします。また、電子カルテ情報やレセプトデータなどの大規模データベースには含まれないデータも多く、ヘルスリテラシー向上の意義など、社会的に重要な意味を持つ分析も可能です。2019年より、100を超える症状・疾患を調査に追加し、より幅広い領域でご活用いただけるようになりました。また、同年調査より研究倫理審査委員会(IRB)の審査も通し、疫学的研究の資料としても利用していただきやすくなっております。
≪引用・転載時のクレジット表記のお願い≫
本リリースの引用・転載時には、必ずクレジットを明記いただけますようお願い申し上げます。
<例> 「医療関連調査会社のメディリードの同社が保有する疾患に関するデータベースを用いたコラムによると・・・」
自主調査レポート
 メディリード / マーケティング&コミュニケーション部
メディリード / マーケティング&コミュニケーション部